■第3回研究交流セミナー
7月1日、亀岡キャンパス・バイオ環境館にて、バイオ環境学部は株式会社日吉(以下、日吉)と共催で「第3回研究交流セミナー」を開催しました。このセミナーには、日吉の役員・社員、インドからの研究インターン2名、そして本学の学生が参加し、国際的な視野を広げ、異文化間の協働を促進する貴重な機会となりました。
セミナーの冒頭、三村徹郎副学長(バイオ環境学部長)が基調講演を行いました。その後、日吉の代表から、会社の基本理念や進行中の環境事業についての紹介がありました。
続いて、インドからのインターンであるSundhar GopuさんとTorel Samyuktha S.さんから、自身の学術的背景や大学、日吉での経験について発表がありました。また、固形廃棄物管理や地震波異方性解析といった、インドで差し迫った環境課題についても取り上げられ、科学的かつ実践的な視点から貴重な知見が提供されました。
学生発表では、Wang Chu Qian(ワン・チュー・チエン)さんから亀岡市内の河川から採取した魚類試料におけるマイクロプラスチックの検出手法を紹介しながら、マイクロプラスチックが人の健康に与える影響についての研究成果が報告されました。眞邉涼子さんからは、ドローン技術を活用した熱中症の危険度を示す暑さ指数(WBGT)推定に関する研究が発表され、その中で気候変動による健康被害を予防する新たな手法が提示されました。
午後には、高澤伸江准教授と永野真理子講師による水環境化学実験が行われました。参加した学生は、排水処理プロセスをミクロで理解するための実験を体験し、研究の現場を肌で感じることができました。その後、鈴木玲治教授とWong Yong Jie講師からバイオ環境館の研究設備の案内や、最先端の研究設備や機器の紹介がありました。
最後に、亀岡キャンパス食堂にて交流会が開催されました。参加者は和やかな雰囲気の中で有意義な交流を楽しみ、国際的なつながりを強めるとともに、産学連携をさらに深める機会となりました。


■株式会社日吉の施設見学
9月3日に、バイオ環境学部の学生11名が滋賀県近江八幡市にある日吉本社を訪問しました。今回の見学は、同社の環境分析・水質管理分野における先進的な取り組みを直接学ぶ貴重な機会となりました。
見学ツアーでは、最先端の研究室が紹介され、環境モニタリングや水質・廃水分析、先進的な試験技術についての説明がありました。学生たちは、大学で学んだ研究概念が産業の現場でどのように応用されているのかを見学し、特に持続可能な水管理、化学分析、環境診断といった分野での具体的な実践内容を学びました。また、PFAS(有機フッ素化合物)検出や環境DNA(eDNA)分析といった先端的な手法も紹介いただき、環境研究における新たなトピックに触れる機会となりました。
さらに、LC-MS/MS 等の高度な機器による水質分析の見学に加え、笹場営農集落排水処理施設で実際の下水処理システムの稼働状況を間近で見学し、学生たちにとって教育的かつ印象的な経験となりました。
今回の見学を通して、学生たちは日吉株式会社の研究者や技術者と積極的に交流したことで、研究と産業が融合し、現実の環境課題にいかに取り組んでいるかについて理解を深めることができました。本学にとっても、産学連携と国際的な視野を広げることができ、意義深い機会となりました。
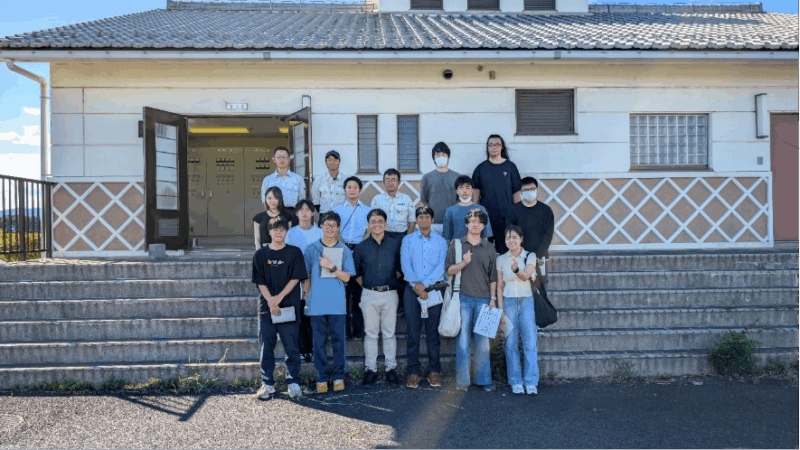

生物環境科学科 坊 安恵 准教授
生物環境科学科 Wong Yong Jie 講師




